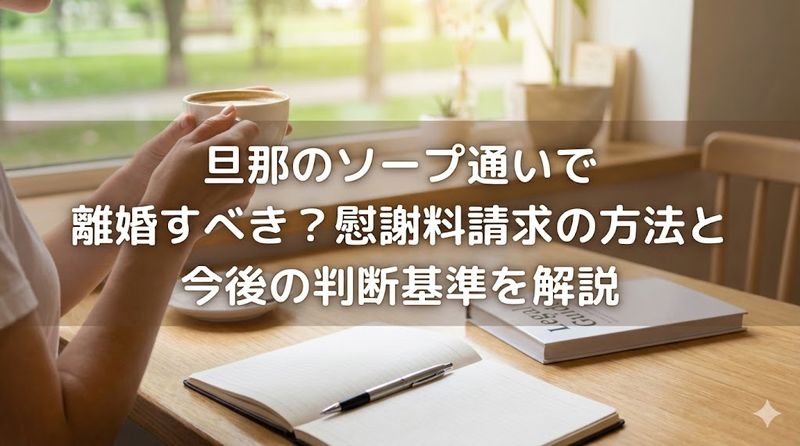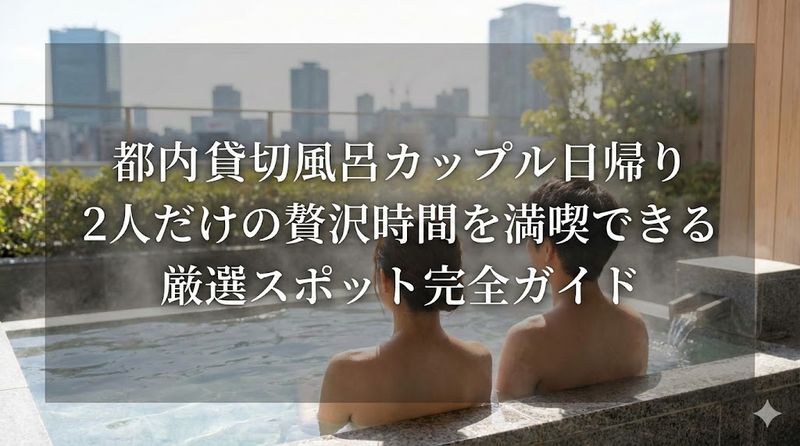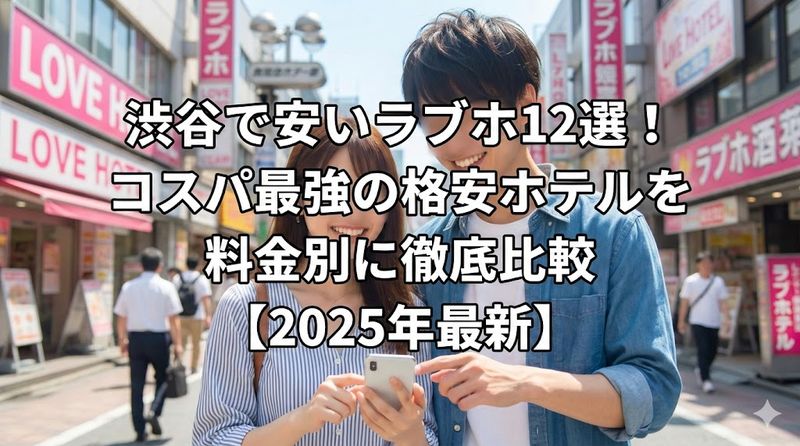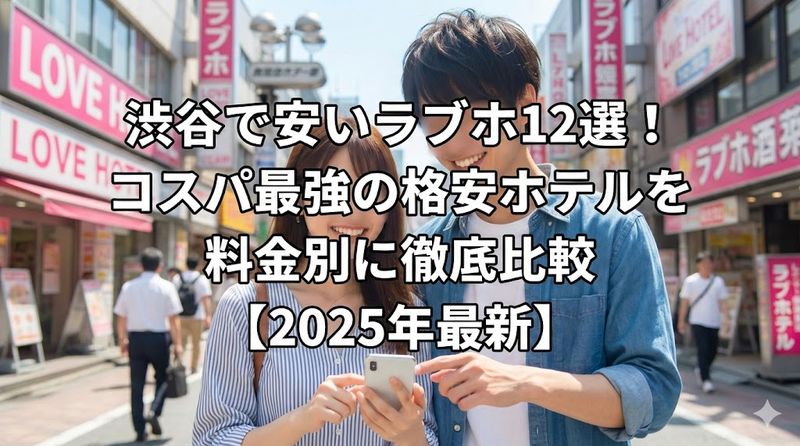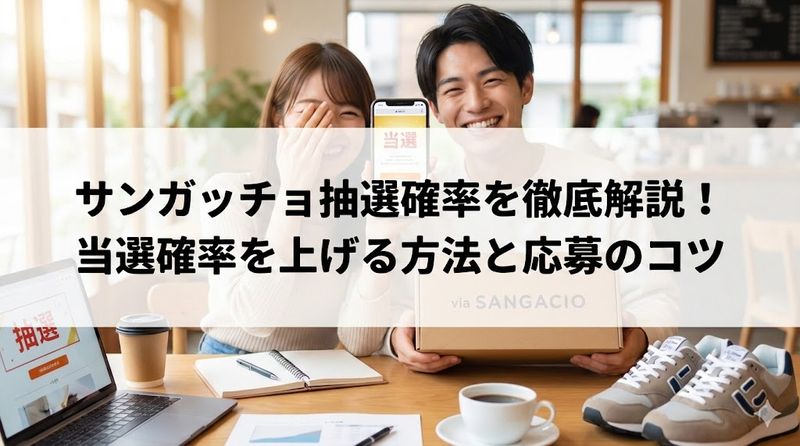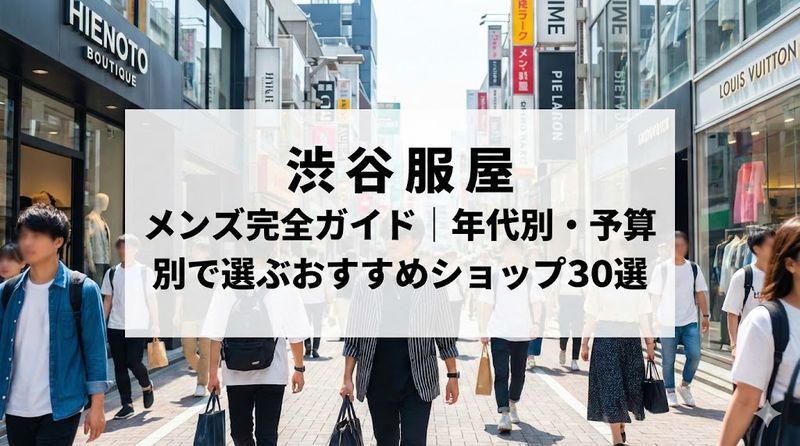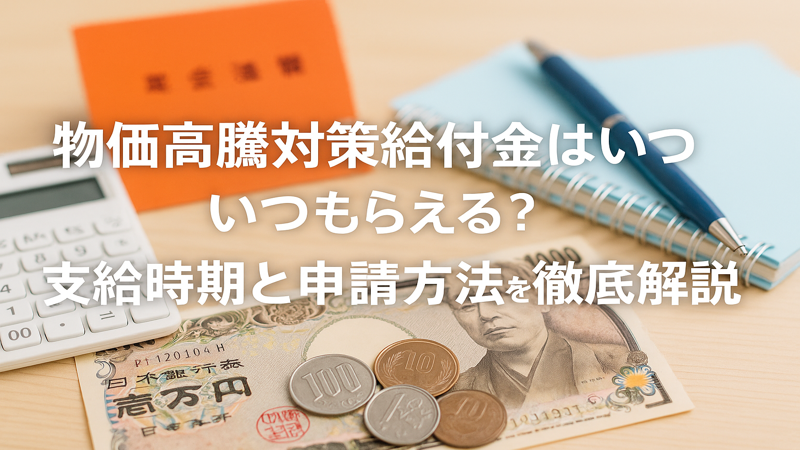
物価高騰の影響で家計が厳しくなり「いつになったら給付金がもらえるの?」と不安に思ったことはありませんか?結論、現在実施中の住民税非課税世帯への給付金は多くの自治体で支給が始まっており、対象世帯には3万円が支給されます。この記事を読むことで給付金の支給時期や申請方法、対象条件などがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
1.物価高騰対策給付金とは

給付金の概要と目的
物価高騰対策給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計負担の軽減を目的とした政府の支援制度です。
特に影響を受けやすい低所得世帯や子育て世帯を対象に、生活の安定を図ることを目的としています。
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押えが禁止され、課税の対象にもなりません。
つまり、受け取った給付金は全額が世帯の生活費として活用できるのです。
対象となる給付金の種類
現在実施されている物価高騰対策給付金には、主に以下の種類があります。
住民税非課税世帯への基本給付として、1世帯あたり3万円が支給されます。
子育て世帯への追加給付として、18歳以下の子ども1人につき2万円が加算されます。
調整給付や不足額給付として、定額減税の恩恵を十分に受けられない世帯への補完的な支援も行われています。
これらの給付金は、世帯の状況に応じて組み合わせて受給できる場合があります。
給付金支給の経緯と法的根拠
この給付金制度は、令和6年12月17日に成立した補正予算に基づく経済対策の一環として実施されています。
物価高騰が長期化する中で、特に影響を受けやすい低所得世帯への緊急的な支援として位置づけられています。
内閣府が主導し、各自治体が実施主体となって給付が行われています。
法的根拠としては、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」が制定され、給付金の保護が図られています。
2.現在実施中の給付金制度

住民税非課税世帯への3万円給付
現在多くの自治体で実施されているのが、住民税非課税世帯への1世帯3万円の給付です。
この給付金は、令和6年12月13日時点で住民登録がある世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯が対象となります。
多くの自治体では2025年2月から3月にかけて支給が開始されており、対象世帯には自治体から通知が送付されています。
申請が不要な世帯には「支給のお知らせ」がはがきで送付され、指定口座に自動的に振り込まれます。
一方で、申請が必要な世帯には「確認書兼申請書」が封筒で送付され、必要事項を記入して返送する必要があります。
子育て世帯への追加給付(2万円加算)
住民税非課税世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人につき2万円が追加で支給されます。
対象となる子どもは、平成18年4月2日以降に生まれた児童です。
例えば、大人2人と子ども2人の4人家族の場合、基本給付3万円+子ども加算4万円(2万円×2人)で、合計7万円が支給されます。
子ども加算は基本給付と同時に支給されるため、別途申請する必要はありません。
ただし、令和7年6月30日までに出生した新生児についても対象となるため、該当する場合は追加申請が必要です。
既に終了した給付金制度について
令和6年度に実施された給付金制度の多くは、2025年6月から7月にかけて申請受付を終了しています。
過去には電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金や、住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付なども実施されていました。
現在は申請受付が終了している制度が多いため、最新の給付金情報については各自治体のホームページを確認することが重要です。
ただし、調整給付や不足額給付については、所得税の確定申告後に支給要件が確定するため、2025年後半まで継続される場合があります。
3.物価高騰対策給付金の支給対象

住民税非課税世帯の条件
住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税の「所得割」と「均等割」の両方で非課税となっている世帯を指します。
単身世帯の場合は、年収が約100万円以下(所得45万円以下)であれば非課税となります。
扶養家族がいる世帯の場合は、「35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円」以下の所得であれば非課税となります。
例えば、夫婦2人世帯の場合は、年収約156万円以下(所得112万円以下)が目安となります。
夫婦と子ども1人の3人世帯の場合は、年収約206万円以下(所得147万円以下)が目安となります。
支給対象外となる世帯
以下の世帯は支給対象外となりますので注意が必要です。
住民税が課税されている親族の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。
これには、親元を離れて暮らしている学生や、単身赴任中の方と離れて暮らしている家族などが含まれます。
他の市町村で同様の給付金を既に受給した世帯も対象外となります。
世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯も対象外となります。
基準日(令和6年12月13日)以降に転出入した世帯については、申請が必要な場合があります。
DV被害者や特別な状況の方への配慮
DV被害者など、配偶者等から暴力を受けて避難している方への特別な配慮もあります。
現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方でも、所定の手続きを行うことで給付金を受け取ることができます。
避難先の自治体の窓口に事前に相談することで、必要な手続きを案内してもらえます。
被害申出受理確認書の発行など、特別な手続きが必要な場合があるため、まずは自治体の相談窓口に連絡することが大切です。
各自治体には女性相談窓口や生活支援課など、専門の相談窓口が設置されています。
4.申請方法と支給時期

申請不要(プッシュ型)での支給
過去の給付金で口座情報を把握している世帯については、申請不要で自動的に支給されます。
対象世帯には「支給のお知らせ」がはがきで送付され、記載された口座に振り込まれます。
支給時期は2025年2月下旬から3月下旬にかけて、自治体ごとに順次実施されています。
振込先口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合のみ、別途手続きが必要です。
口座が凍結されている場合などで振込ができなかった世帯には、別途案内が送付されます。
申請が必要な場合の手続き
申請が必要な世帯には、「確認書兼申請書」が封筒で送付されます。
必要事項を記入・押印し、本人確認書類と振込先口座の写しを添付して返送します。
申請期限は多くの自治体で令和7年5月30日頃となっていますが、自治体により異なります。
オンライン申請に対応している自治体では、二次元バーコードからアクセスして申請できます。
申請書の不備がある場合は、自治体のコールセンターから連絡がありますので、期限内に修正が必要です。
支給時期の目安と振込スケジュール
申請不要の世帯については、2025年2月下旬から3月下旬にかけて順次支給されています。
申請が必要な世帯については、申請書受理から約4週間程度で支給されます。
支給が集中する時期(申請期限間近など)は、処理に時間がかかる場合があります。
振込先口座の確認に時間がかかる場合や、書類不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
支給状況については、各自治体のホームページで随時更新されていますので、定期的に確認することをお勧めします。
5.今後の給付金制度と政策動向

2025年に検討されている一律給付
2025年6月に石破首相が指示した国民一律2万円の給付が注目されています。
この給付金は全国民を対象とし、子育て世帯や住民税非課税世帯にはさらに2万円の加算も検討されています。
しかし、現時点では検討段階であり、具体的な支給時期は未定です。
実施が決定された場合でも、早くても2025年度後半以降の支給になると見込まれています。
財源の確保や経済効果の検証など、慎重な検討が続けられています。
政府の継続的な支援方針
石破首相は「物価高対策としての現金給付をいつまで続けるかは申し上げない」と発言しており、継続的な支援の姿勢を示しています。
賃金上昇が物価上昇を上回るまで、状況に応じて柔軟に対応する方針が示されています。
2025年参議院選挙では、与党・自民党が「一律給付金」、野党・立憲民主党が「消費税ゼロ+給付金」を掲げており、物価高対策が大きな争点となっています。
給付金の即効性と消費税減税の持続的効果、それぞれのメリット・デメリットが議論されています。
電気・ガス料金補助など他の物価高対策
給付金以外の物価高対策として、電気・ガス料金の補助も実施されています。
2025年7月から9月までの3か月間、電気・ガス料金の支援が再開される予定です。
ガソリン価格補助については、2025年5月から実施されており、1リットルあたり10円の補助が行われています。
標準家庭で月最大950円程度の負担軽減効果が期待されています。
これらの支援策は、物価高騰の状況や燃料価格の動向を見ながら、継続的に検討されています。
まとめ
この記事で紹介した物価高騰対策給付金について、重要なポイントをまとめます。
• 住民税非課税世帯への3万円給付は現在多くの自治体で実施中
• 18歳以下の子どもがいる世帯には1人につき2万円が追加支給
• 申請不要の世帯には2025年2月下旬から3月下旬にかけて順次支給
• 申請が必要な世帯には確認書兼申請書が送付され、期限内の提出が必要
• 給付金は差押え禁止・非課税で、全額が生活費として活用可能
• DV被害者など特別な状況の方への配慮制度も整備されている
• 2025年の一律給付は検討段階で、具体的な支給時期は未定
• 電気・ガス料金補助など他の物価高対策も並行して実施中
物価高騰の影響を受けている皆さんにとって、これらの給付金制度は大きな支援となるはずです。
対象となる可能性がある方は、お住まいの自治体からの通知を必ず確認し、申請が必要な場合は期限内に手続きを完了させてください。
最新の情報は各自治体のホームページで随時更新されていますので、定期的にチェックすることをお勧めします。