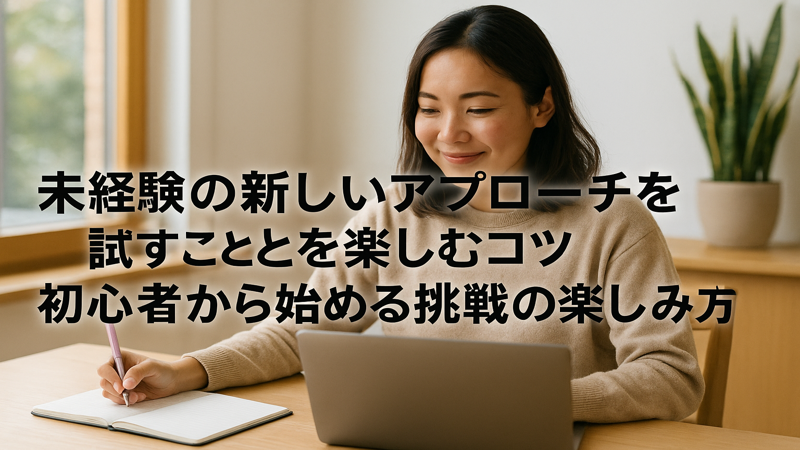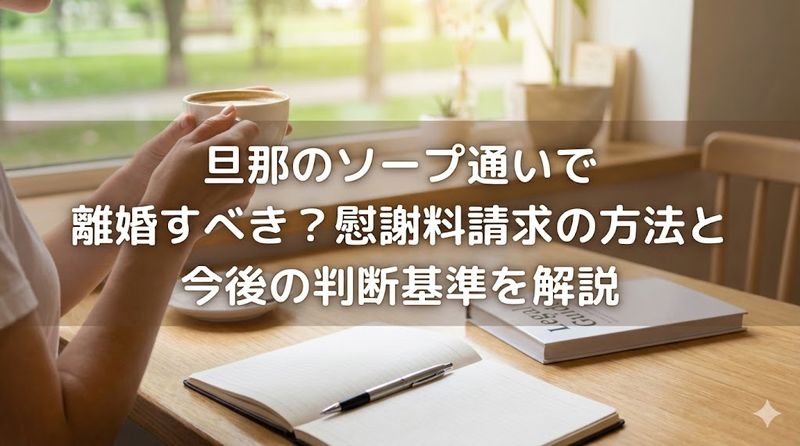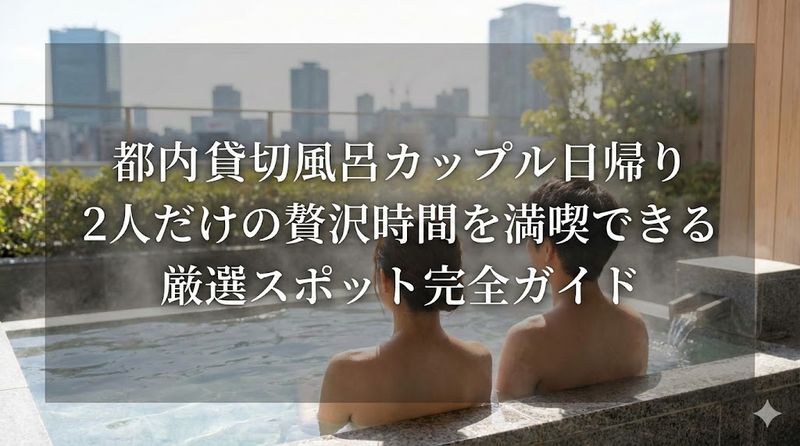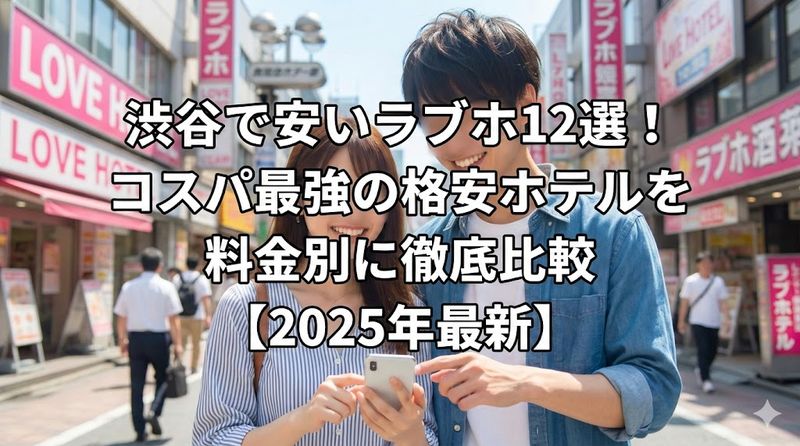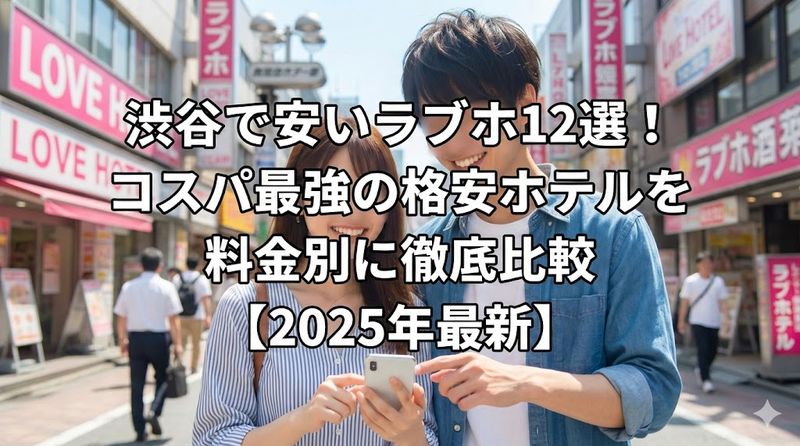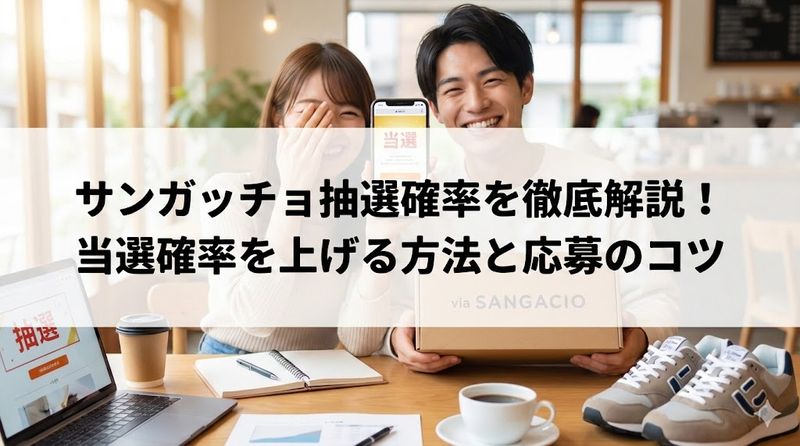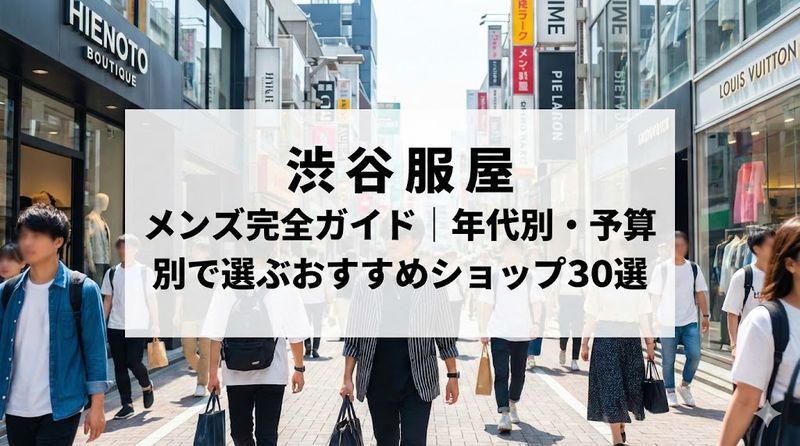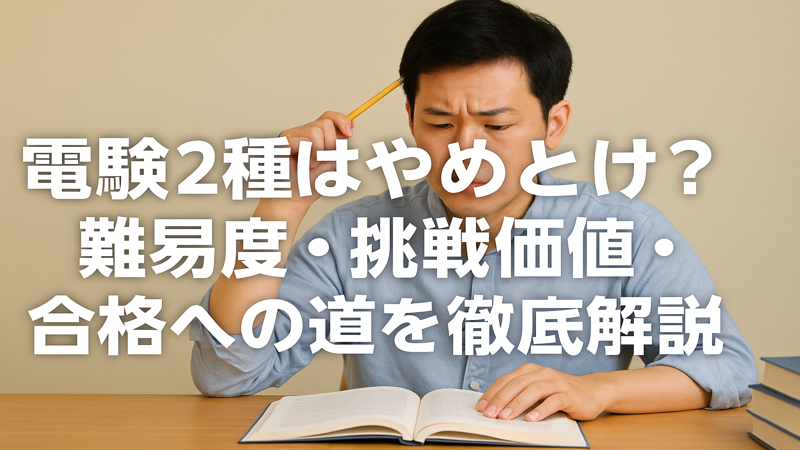
あなたは「電験2種に挑戦したいけど、やめとけと言われて不安」と思ったことはありませんか?結論、電験2種は確かに難関資格ですが、適切な戦略で合格は可能です。この記事を読むことで電験2種の実態と挑戦する価値、効率的な合格戦略がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.電験2種が「やめとけ」と言われる5つの理由

合格率わずか数%という圧倒的な難易度
電験2種の合格率は一次試験で約30%、二次試験で約20%、総合合格率は約6~8%程度という非常に厳しい数字となっています。
この低い合格率の背景には、出題範囲の広さと問題の難易度の高さがあります。
一次試験は理論・電力・機械・法規の4科目、二次試験は電力・管理と機械・制御の2科目で構成されており、すべてにおいて高度な知識と応用力が求められます。
特に二次試験は記述式のため、単に知識を暗記するだけでなく、論理的に説明する能力も必要です。
多くの受験者が何年も挑戦を続けており、一発合格はほぼ不可能に近いと言われています。
電験2種の勉強に必要な時間は1000時間以上
電験2種に合格するためには、一般的に1000~2000時間の勉強時間が必要とされています。
電験3種を既に取得している場合でも、最低1000時間は確保すべきでしょう。
1日2時間勉強したとしても、約1年半から3年近くかかる計算になります。
仕事をしながら勉強する社会人にとって、この時間を確保することは大きな負担です。
休日も勉強に充てる必要があり、プライベートの時間が大幅に削られることになります。
家族がいる方の場合、理解と協力を得ることも重要な課題となるでしょう。
高額な受験費用と参考書代の負担
電験2種の受験には、一次試験が12,800円、二次試験が20,800円の受験料がかかります。
科目合格制度を利用して複数年受験する場合、その都度費用が発生します。
さらに参考書や問題集の購入費用として、最低でも3~5万円程度は必要です。
通信講座を利用する場合は、10万円から30万円程度の費用がかかることもあります。
合格までに3年かかると仮定すると、トータルで10万円以上の投資が必要になります。
このコストに見合うリターンが得られるかどうか、慎重に検討する必要があります。
実務経験がないと資格を活かせない現実
電験2種を取得しても、実務経験がなければ電気主任技術者として選任されることは困難です。
多くの企業は、資格保有者であっても実務経験を重視します。
特に高圧受電設備や変電設備の保守管理には、実践的なスキルと知識が不可欠だからです。
資格を取得しただけで即座に独立開業できるわけでもありません。
資格取得と並行して、実務経験を積める環境に身を置くことが重要になります。
現在の職場で電気関連の業務に携われない場合、転職も視野に入れる必要があるかもしれません。
科目合格制度でも3年以内に全科目合格が必須
電験2種には科目合格制度があり、一度に全科目合格する必要はありません。
しかし、最初の科目合格から3年以内にすべての科目に合格しなければ、それまでの合格は無効になります。
この期限があることで、計画的な学習が求められます。
1科目でも落とすと、次の年に再挑戦しなければならず、スケジュールが狂ってしまいます。
仕事や家庭の事情で勉強時間が確保できなくなると、3年という期限はあっという間に過ぎてしまいます。
モチベーションを維持し続けることの難しさも、多くの受験者が直面する課題です。
2.電験2種の難易度と合格率の実態

電験2種の試験科目と出題範囲
電験2種の一次試験は、理論・電力・機械・法規の4科目で構成されています。
理論では電気回路、電磁気学、過渡現象など、電気工学の基礎理論を深く学びます。
電力科目では発電、送配電、変電に関する知識が問われ、実際の電力システムの運用に関する理解が必要です。
機械科目は電動機、変圧器、パワーエレクトロニクスなど、電気機器全般をカバーします。
法規では電気事業法、電気設備技術基準など、法的知識が求められます。
二次試験は電力・管理と機械・制御の2科目で、すべて記述式となっており、計算問題と論述問題が出題されます。
過去5年間の合格率データ分析
過去5年間のデータを見ると、一次試験の合格率は25~35%、二次試験の合格率は15~25%程度で推移しています。
一次試験の科目別では、理論と機械が特に難易度が高く、合格率が低い傾向にあります。
二次試験については年度によって難易度のばらつきがあり、合格率が10%台前半になることもあります。
最終的な総合合格率は6~8%程度であり、国家資格の中でも最難関クラスと言えます。
| 年度 | 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | 総合合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 28.5% | 18.3% | 7.2% |
| 2022年 | 31.2% | 21.7% | 8.1% |
| 2021年 | 26.8% | 16.9% | 6.5% |
受験者数は毎年1万人前後で、そのうち最終合格者は600~800人程度です。
電験3種との難易度の違い
電験3種の合格率が8~12%程度であるのに対し、電験2種は約6~8%とさらに低くなっています。
出題範囲は電験3種とほぼ同じですが、問題の難易度と計算の複雑さが格段に上がります。
電験3種はマークシート方式ですが、電験2種の二次試験は記述式のため、解答プロセスも採点対象となります。
電験3種で問われるのは基本的な理解ですが、電験2種では応用力と実践的な問題解決能力が求められます。
電験3種合格者でも、電験2種には数年かかるというケースが一般的です。
難易度の差は単なる知識量の違いではなく、質的な理解の深さの違いと言えるでしょう。
独学と通信講座の合格率比較
独学での合格率は公式データがありませんが、体感的には3~5%程度と言われています。
通信講座や予備校を利用した場合、サポート体制により合格率は10~15%程度まで上がるとの報告もあります。
独学のメリットは費用を抑えられることですが、学習計画の立案や疑問点の解決を自力で行う必要があります。
通信講座では添削指導や質問対応が受けられるため、効率的に学習を進められる点が大きなメリットです。
- 独学:費用が安い、自分のペースで学習できる、孤独で挫折しやすい
- 通信講座:サポートが手厚い、学習計画が立てやすい、費用が高い
- 予備校:講師に直接質問できる、仲間ができる、通学の時間と費用がかかる
自分の学習スタイルや経済状況に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。
3.それでも電験2種に挑戦する価値がある人

電験2種取得後のキャリアアップと年収
電験2種を取得すると、電気主任技術者として高圧・特別高圧の電気設備を扱えるようになります。
大規模工場やビル、発電所などで電気設備の保安監督者として活躍できます。
年収面では、電験2種保有者は平均500~700万円程度とされていますが、独立開業すれば1000万円以上も可能です。
企業に勤める場合でも、資格手当として月2~5万円程度が支給されることが多いです。
管理職への昇進においても、電験2種は大きなアドバンテージとなります。
定年後も技術顧問として働ける可能性が高く、長期的なキャリア形成に有利な資格と言えます。
電験2種でできる独占業務と就職先
電験2種の独占業務は、電圧50,000V未満の事業用電気工作物の保安監督です。
具体的には、ビル、工場、病院、商業施設などの高圧受電設備の点検・保守・管理が該当します。
主な就職先としては以下のようなものがあります。
- 電力会社・発電事業者
- 大手製造業の工場
- ビル管理会社
- 電気保安協会
- 電気設備工事会社
- 独立開業(電気管理技術者)
電気主任技術者の需要は安定しており、特に高齢化により若手技術者の需要が高まっています。
資格があれば求人は豊富で、転職市場でも非常に有利に働きます。
電気主任技術者の需要と将来性
日本国内には約80万件の自家用電気工作物があり、すべてに電気主任技術者の選任が法律で義務付けられています。
しかし電験2種保有者は全国で約2万人程度しかおらず、慢性的な人手不足の状態です。
再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電所や風力発電所でも電気主任技術者が必要とされています。
2050年カーボンニュートラルに向けた動きにより、電気設備の需要はさらに拡大する見込みです。
電気主任技術者の高齢化も進んでおり、若手・中堅層の確保が業界全体の課題となっています。
AIや自動化が進んでも、最終的な保安責任は人が担う必要があるため、資格の価値が下がることは考えにくいです。
電験2種が向いている人の特徴
電験2種に向いているのは、数学や物理が得意で、論理的思考ができる人です。
複雑な計算問題を解くことに抵抗がなく、むしろ楽しめる人は適性があります。
長期的な目標に向けて地道に努力を続けられる忍耐力も重要な資質です。
電気工学に純粋な興味関心がある人は、勉強自体が苦にならず、モチベーションを維持しやすいでしょう。
すでに電気関連の実務経験がある人は、理論と実践を結びつけやすく、理解が深まりやすいです。
安定した専門職としてのキャリアを築きたい人にとっては、時間と労力をかける価値がある資格と言えます。
4.電験2種合格のための現実的な戦略
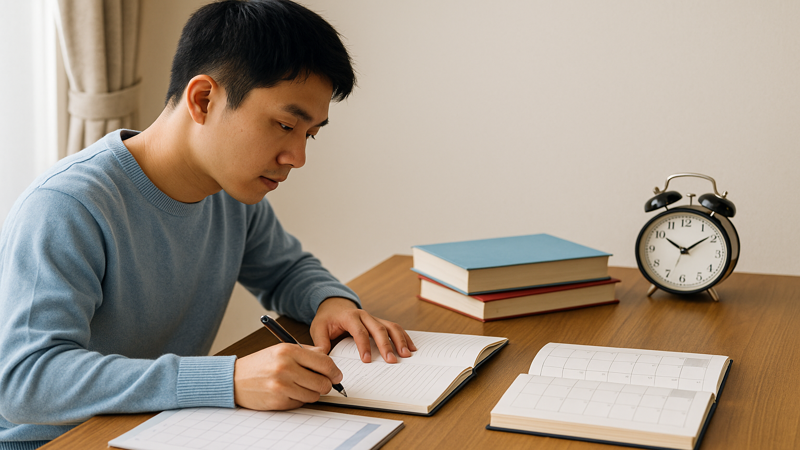
科目合格制度を活用した3年計画
電験2種には科目合格制度があるため、一度にすべて合格する必要はありません。
効率的な戦略は、1年目に一次試験の2科目、2年目に残りの2科目、3年目に二次試験を受験する方法です。
具体的には以下のようなプランが考えられます。
1年目(一次試験)
- 理論と機械の2科目に集中
- 1日2~3時間、年間800~1000時間の勉強
2年目(一次試験)
- 電力と法規の2科目に集中
- 1年目の貯金を活かして効率的に学習
3年目(二次試験)
- 一次試験の知識を総復習しながら記述対策
- 過去問演習と論述練習に重点を置く
この方法なら、各年の負担を分散でき、仕事との両立も可能です。
効率的な勉強法と時間配分のコツ
電験2種の勉強では、基礎理論の理解→公式の暗記→問題演習という順序が重要です。
いきなり難しい問題に取り組むのではなく、まずは教科書レベルの基礎を固めましょう。
時間配分としては、インプット3割、アウトプット7割を意識すると効果的です。
朝の通勤時間や昼休みなど、スキマ時間を活用して公式の暗記や復習を行います。
まとまった時間が取れる週末は、過去問や予想問題に取り組み、実戦力を養います。
間違えた問題は必ずノートにまとめ、定期的に見返すことで、弱点を克服できます。
二次試験対策では、答案の書き方も重要なので、実際に手を動かして記述練習をしましょう。
おすすめの参考書と過去問題集
電験2種の定番参考書として、「これだけシリーズ」(電気書院)があります。
各科目の重要ポイントがまとめられており、初学者から経験者まで幅広く使えます。
過去問題集は、「電験2種過去問詳解」(電気書院)が最もおすすめです。
10年分の過去問が詳しい解説付きで掲載されており、出題傾向の把握に役立ちます。
二次試験対策には、「電験2種二次試験の完全研究」が有効です。
- 一次試験:「これだけシリーズ」各科目 + 過去問10年分
- 二次試験:「二次試験の完全研究」+ 記述式過去問
- 補助教材:YouTube動画、オンライン講座
最低限これらの教材を完璧にマスターすれば、合格ライン到達は可能です。
挫折しないためのモチベーション管理術
長期戦となる電験2種の勉強では、モチベーション維持が最大の課題です。
目標を細分化し、小さな成功体験を積み重ねることで、やる気を保ちやすくなります。
例えば「今週は理論の第3章を終わらせる」といった具体的な目標設定が効果的です。
SNSやブログで学習記録を公開することで、適度なプレッシャーと仲間意識が生まれます。
同じ目標を持つ仲間とオンラインやリアルで交流することも、モチベーション維持に有効です。
スランプに陥ったときは、無理せず一度休憩を取る勇気も必要です。
「なぜ電験2種を取りたいのか」という初心を定期的に思い出すことで、長期的な努力を続けられます。
まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 電験2種の合格率は約6~8%で、国家資格の中でも最難関クラスである
- 合格には1000~2000時間の勉強が必要で、長期的な計画と努力が求められる
- 受験費用と参考書代を含めると、トータル10万円以上の投資が必要になる
- 実務経験がないと資格を活かせないため、資格取得と並行して経験を積むことが重要
- 電験2種保有者の年収は平均500~700万円で、独立すれば1000万円以上も可能
- 電気主任技術者は慢性的な人手不足で、需要は今後も安定している
- 科目合格制度を活用した3年計画で、仕事との両立を図ることができる
- 効率的な勉強法は「基礎理論の理解→公式の暗記→問題演習」の順序を守ること
- おすすめ参考書は「これだけシリーズ」と「電験2種過去問詳解」である
- モチベーション維持のためには、小さな目標設定と仲間との交流が有効である
電験2種は確かに難関資格ですが、適切な戦略と継続的な努力があれば合格は十分可能です。あなたの将来のキャリアを大きく広げる可能性を秘めた資格ですので、ぜひ前向きに挑戦を検討してみてください。
関連サイト
一般財団法人 電気技術者試験センター