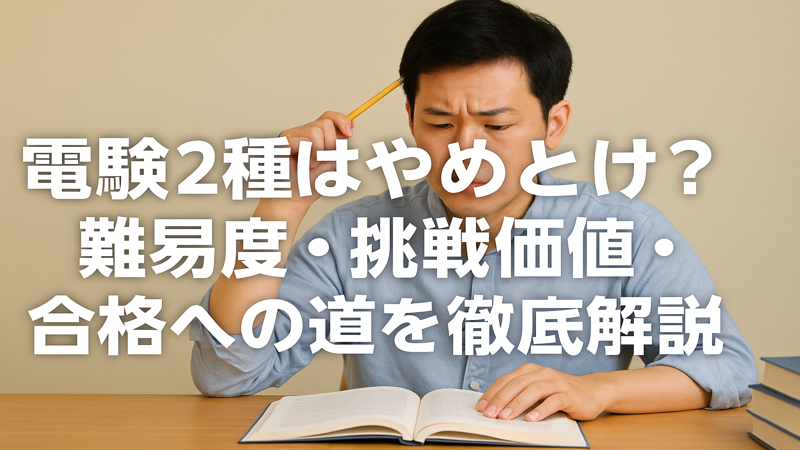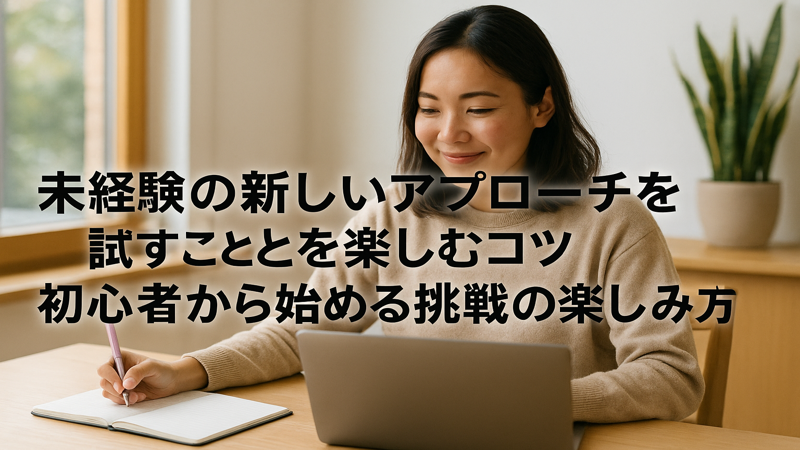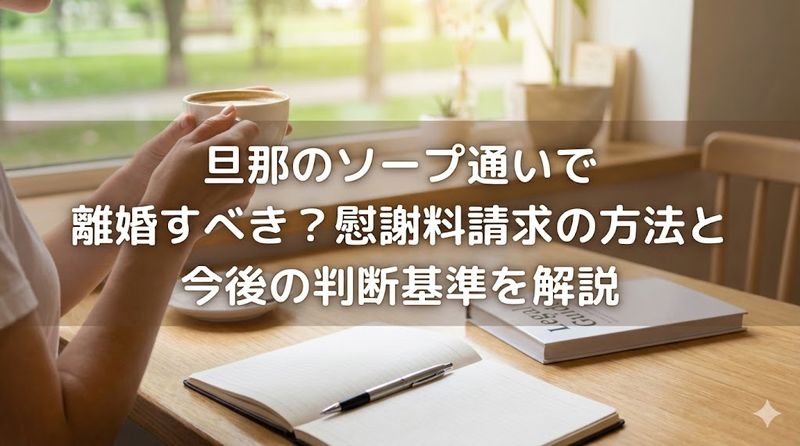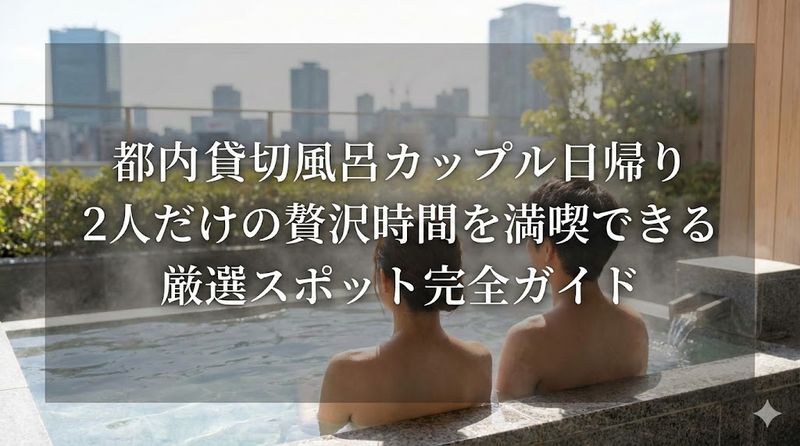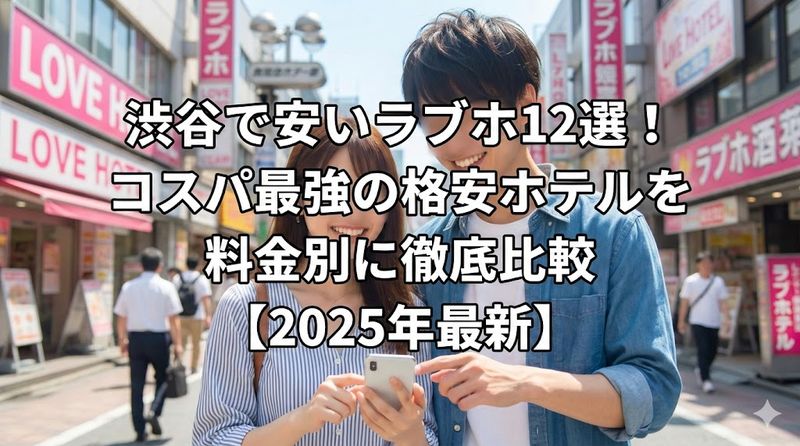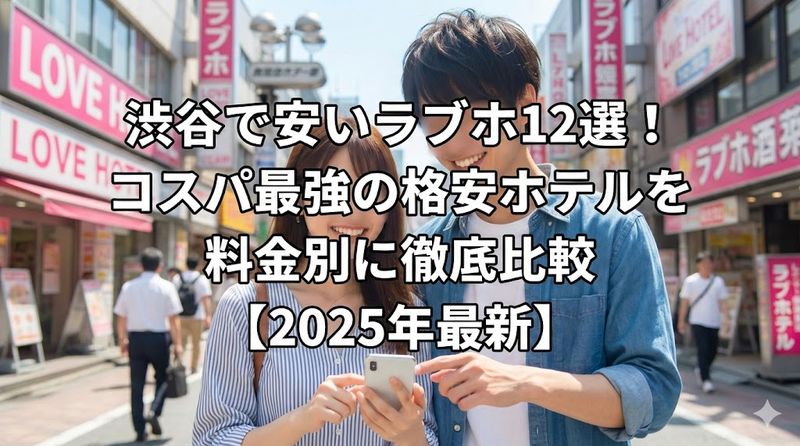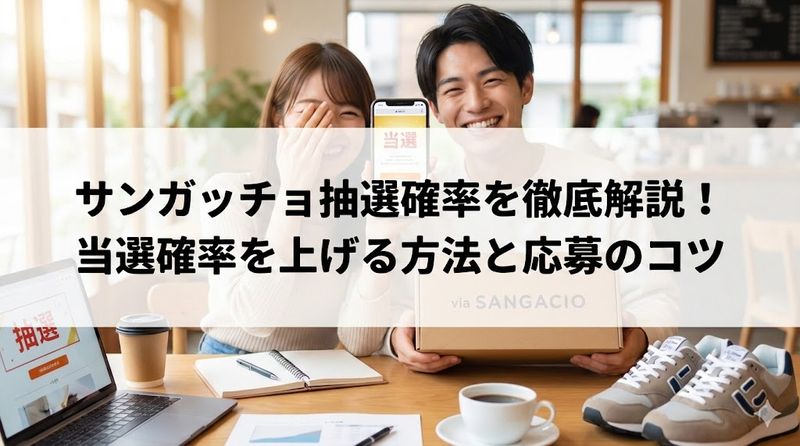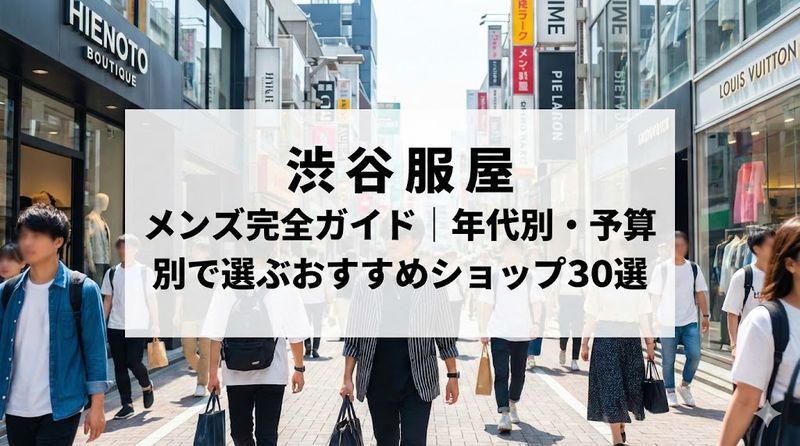あなたは「かねへんに易と書く漢字の読み方が分からない」と困ったことはありませんか?結論、この漢字は「錫」と書いて「すず」や「シャク」と読みます。この記事を読むことで、錫の正しい読み方や意味、書き順、熟語での使い方まで完全に理解できるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.「錫」の読み方

訓読みは「すず」
「錫」の訓読みは「すず」です。
これは金属元素の一つであるスズを表す読み方で、最も一般的な読み方といえます。
日常生活では「錫の器」や「錫製品」といった形で使われることが多く、覚えやすい読み方です。
元素記号では「Sn」と表記され、銀白色の光沢を持つ柔らかい金属として知られています。
音読みは「シャク」「セキ」「シ」
「錫」の音読みには「シャク」「セキ」「シ」があります。
最も頻繁に使われるのは「シャク」で、仏教用語の「錫杖(しゃくじょう)」などで使用されます。
「セキ」は「鉛錫(えんせき)」などの専門用語で見られる読み方です。
「シ」という読み方は比較的使用頻度が低いものの、古典的な文献などで見かけることがあります。
表外読みとその他の読み方
「錫」には表外読みとして「たまもの」という読み方もあります。
これは「賜物(たまもの)」と同じ意味で、上位者から下位者へ何かを与えることを表します。
また、「たま(う)」と読んで「賜う」の意味で使われることもあります。
これらの読み方は現代ではあまり見かけませんが、古典や漢文を読む際には知っておくと役立ちます。
2.「錫」の意味とは

金属元素の「スズ」を表す
「錫」の最も代表的な意味は金属元素の「スズ」です。
スズは原子番号50、元素記号Snの金属で、銀白色の光沢を持ち、非常に柔らかく展延性に優れています。
融点が約232℃と低いため、古くからはんだや合金材料として利用されてきました。
ブリキ(鉄板に錫メッキを施したもの)や青銅(銅と錫の合金)など、私たちの生活に身近な製品に使われています。
僧侶が持つ杖「錫杖」の意味
「錫」には僧侶や道士が用いる杖という意味もあります。
「錫杖(しゃくじょう)」は仏教の僧侶が持つ杖で、上部に金属製の輪がついており、歩く際に音を鳴らします。
この音によって邪悪なものを払い、また自分の存在を知らせることで小動物を踏まないようにする配慮も込められています。
修行僧が旅をする際の必需品として、古くから使われてきた重要な仏具の一つです。
「賜る・たまもの」の意味もある
「錫」には「賜る」「たまもの」という意味もあります。
これは「賜」という漢字と通じる意味で、目上の人から目下の人へ何かを与えることを表します。
古代中国の「九錫(きゅうしゃく)」は、天子が功績のあった臣下に与える九種類の宝物を指す言葉です。
「天錫(てんしゃく)」は天から授けられた恩恵や賜物という意味で使われます。
3.「錫」の書き方と基本情報

部首は「かねへん(金部)」
「錫」の部首は「かねへん(金部)」です。
金属に関連する漢字に使われる部首で、「金」「銀」「銅」「鉄」などの仲間です。
かねへんは左側に配置され、右側に「易」という文字が組み合わさって「錫」という漢字が成り立っています。
金属を表す漢字の多くがこの部首を持つため、覚えておくと他の漢字も推測しやすくなります。
画数は16画
「錫」の総画数は16画です。
左側の「金」が8画、右側の「易」が8画で、合計16画となります。
漢字検定では準1級レベルに分類される、やや難易度の高い漢字です。
画数が多い漢字ですが、「かねへん」と「易」の組み合わせと覚えれば書きやすくなります。
正しい書き順を確認しよう
「錫」の正しい書き順は左側のかねへんから書き始めます。
まず「金」の部分を8画で書き終えてから、右側の「易」を上から順に書いていきます。
「易」は「日」の部分を先に書き、その下に「勿」の部分を続けて書くのが正しい順序です。
書き順を守ることで、バランスの良い美しい字形になり、書くスピードも上がります。
人名用漢字として使える
「錫」は人名用漢字に指定されています。
2004年9月に戸籍法施行規則により、名前に使える漢字として正式に定められました。
「すず」という読み方で女性の名前に使われることが多く、「美錫(みすず)」などの名前があります。
柔らかく美しい金属のイメージから、優しさや輝きを願って名付けられることが多い漢字です。
4.「錫」を使った熟語と使い方

錫杖(しゃくじょう)
錫杖(しゃくじょう)は僧侶が持つ杖のことです。
上部に金属製の輪がついており、歩く際にシャラシャラと音を鳴らします。
この音によって虫や小動物を驚かせて踏まないようにしたり、邪気を払ったりする役割があります。
お遍路さんや修行僧が旅をする際に必ず携帯する、仏教における重要な法具の一つです。
錫婚式(すずこんしき)
錫婚式(すずこんしき)は結婚10周年を祝う記念日です。
結婚記念日には年数ごとに名前がついており、10年目が錫婚式と呼ばれます。
錫のように美しく柔らかく、お互いに歩み寄れる関係を表現しています。
この日には錫製の食器や酒器などを贈り合う習慣があり、夫婦の絆を再確認する大切な節目とされています。
巡錫(じゅんしゃく)・天錫(てんしゃく)
巡錫(じゅんしゃく)は僧侶が各地を巡り歩くことを意味します。
「錫」が僧侶の杖を表すことから、錫杖を持って巡る様子を表現した言葉です。
高僧が各地の寺院を訪問したり、修行のために旅をしたりすることを指します。
天錫(てんしゃく)は天から授けられる恩恵や賜物という意味で、天の恵みを表す格調高い言葉です。
錫器・錫箔など実用的な熟語
錫器(すずき)は錫で作られた器や道具のことです。
日本酒の徳利やぐい呑み、茶道具などに使われ、高級な酒器として珍重されています。
錫箔(すずはく)は錫を薄く延ばして箔状にしたもので、かつては針を包む包装材などに使われていました。
その他にも錫石(すずいし)は錫の主要な鉱石、鉛錫(えんせき)は鉛と錫の合金を指すなど、専門的な場面でも使われます。
まとめ
- 「錫」は「かねへんに易」と書き、「すず」「シャク」「セキ」などと読む
- 主な意味は金属元素のスズ、僧侶の杖、賜物の3つ
- 部首は「かねへん(金部)」で、総画数は16画
- 人名用漢字として名前にも使用できる
- 「錫杖」は僧侶が持つ杖、「錫婚式」は結婚10周年の記念日
- 「巡錫」は僧侶が各地を巡ること、「天錫」は天からの恵み
- 錫器や錫箔など、実用的な製品名にも使われる
- 音読みの「シャク」は仏教用語で、訓読みの「すず」は金属名で使われる
- 柔らかく美しい金属のイメージから、名前にも好んで使われる
「錫」という漢字について理解が深まりましたね。日常生活ではあまり見かけない漢字かもしれませんが、仏教文化や伝統工芸品、結婚記念日など、日本文化のさまざまな場面で使われている興味深い漢字です。ぜひこの知識を活かしてくださいね。